恵み
- 泉清隆
- 2017年4月28日
- 読了時間: 2分
太平洋戦争が終わって間もないころ、ある女性が単身ニユーヨークに留学しました。
ところが、人種差別と戦争の余波で精神的重圧が重なり、肺結核にかかってしまったのです。医者に「すぐに手術を受けなければ、手遅れになる。モンロヴィアにアメリカ1のサナトリウムがあるから、そこに行きなさい。」と言われましたが、そんな旅費なんてありません。
しかし、留学生仲間がカンパしてくれ、自分達の食べる分も減らし分け与え、治療費は後で日本から送ってもらう約束を取り付けて、彼女は旅立つことになりました。巨大なアメリカ大陸を東から西への特急列車、五泊車中で過ごす長旅、病人にとっては苛酷な旅です。
まして彼女はお金もなかったのです。彼女の持参した食料も三日でなくなり、車掌さんにジュ-スを頼みました。車掌さんは彼女をジーッと見て「あんたは病気だね?どこが悪い?」と尋ね、ジュースを持ってきて「お金はいらないよ」と言い立ち去りました。あくる日の朝、またジュースとサンドウィッチをもってきて「お金はいらないよ」とただ一言。その後で、「どこに行く?」と聞かれたので、終点のロサンゼルスからしばらくバスに乗ってモンロヴィアの病院へ行くと彼女は告げました。
彼女が乗っている列車は、あくる日の夕刻に終点のロサンゼルスに着く予定でした。すると突然、アナウンスで「皆様、この列車にモンロヴィアの病院へ行く、日本人留学生が乗っています。ワシントン鉄道省に連絡し、会議したところ、臨時停車せよということになりましたので、明日一番に停車するのはロスではなく、モンロヴィアです。」と流れました。
その夜、車掌さんはたくさんの重い荷物を手早くまとめ、降車口に運んで下さったそうです。夜明けとともにモンロヴィアに到着すると、車椅子が用意されていました。そして、列車の窓という窓から、いろんな人が!名刺や電話番号、住所を書いたメモ、何十ドルかの札が投げられ、「必ず治るよ、頑張って!困ったら、連絡しなさい。」口々にそんな言葉が贈られました。彼女は涙があふれ、視界が見えなくなり、いつまでも列車を見送ったそうです。闘病生活の三年間、見舞い客が絶えることなくきてくれたそうです。見舞い客とは、列車で一緒になった人々でした。さらに、莫大な手術、入院費用は、誰かの手によって、支払われていたそうです。 (犬養道子さんの話し)
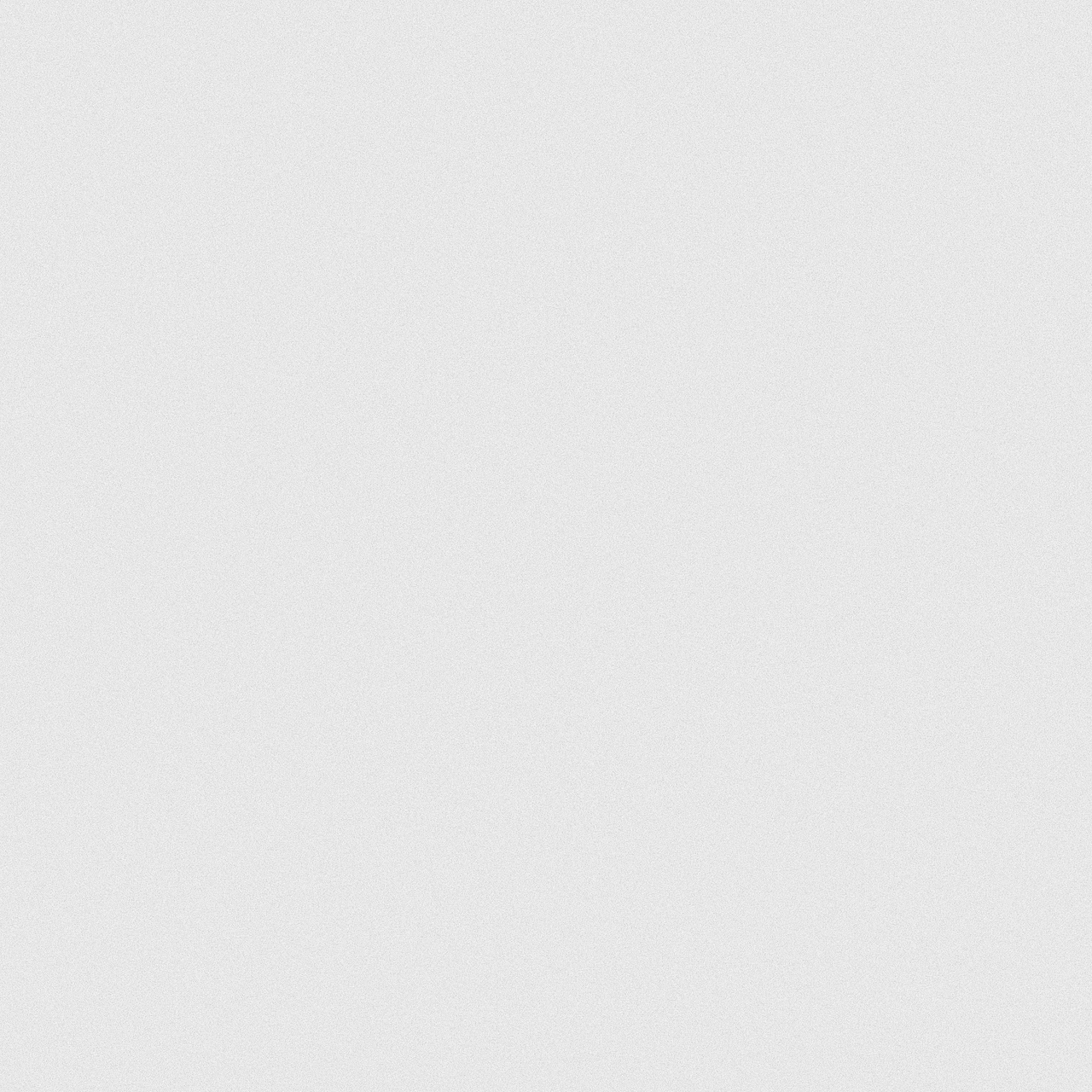

コメント